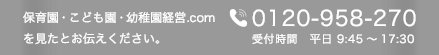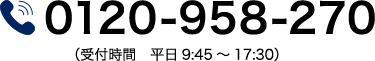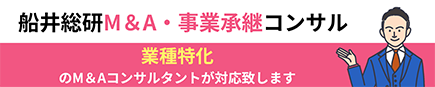2025年に向けた認定こども園・幼稚園経営の羅針盤:生き残りをかけた戦略とは?
- テーマ:
- 時流・業界動向
本コラムをお読みいただきありがとうございます。船井総合研究所の認定こども園・幼稚園コンサルタント、島崎卓也です。
はじめに
2025年、日本の少子化はますます深刻化し、保育業界は大きな転換期を迎えます。出生数の減少は、園児数の減少に直結し、各園の経営を圧迫する要因となります。
この厳しい環境下で、認定こども園・幼稚園が生き残り、さらなる発展を遂げるためには、時代の変化を的確に捉え、戦略的な経営を実践していくことが不可欠です。
本コラムでは、最新の業界動向を踏まえ、2025年に向けた経営戦略のポイントをご紹介します。
業界の時流についての解説
1. 少子化の加速と園児獲得競争の激化
2023年の出生数は過去最少の72.7万人となり、合計特殊出生率も1.20と過去最低を記録しました。 少子化は今後も加速する見込みであり、2024年の出生数は70万人を下回る可能性も高いです。
この少子化の影響は、すでに私立幼稚園の就園者数減少として顕著に表れており、令和5年度には70万人台にまで落ち込んでいます。 一方で、幼保連携型認定こども園の在園者数は増加傾向にあり、令和5年度には初めて幼稚園の在園者数を上回りました。
2. 幼稚園の縮小と認定こども園への移行
少子化の影響を受け、幼稚園の学校数は減少傾向にあります。特に、在園児数が少ない小規模園の割合が増加しており、令和5年度には初めて「1~50人」規模の園が最多となりました。これは、各園の園児数が減少傾向にあることを示唆しています。
このような状況下、幼稚園から幼保連携型認定こども園への移行が進んでいます。しかし、幼保連携型認定こども園の増加も近年は落ち着きを見せており、全国の待機児童数が減少していることを踏まえると、今後の伸びは緩やかになると予測されます。つまり、これから認定こども園への移行は難しくなると考えられます。
3. 経営の効率化と財務基盤の強化
少子化による園児数減少は、各園の経営を圧迫する大きな要因となります。
このような状況下で生き残りを図るためには、経営の効率化と財務基盤の強化が不可欠です。
具体的には、
収支の見える化によるコスト削減
業務の標準化による人材配置の最適化
ICT 導入による業務効率の向上
多様な収入源の確保
などが挙げられます。
今後の予測:2025年の認定こども園・幼稚園業界はどうなる?
2025年に向けて、認定こども園・幼稚園業界では以下のような変化が予測されます。
1. 1号認定子どもの激減と低年齢児への需要の高まり
3歳児以上の幼児教育・保育の無償化に伴い、1号認定子ども(幼稚園児)は今後ますます減少すると予想されます。 一方で、共働き世帯の増加などを背景に、0~2歳児の保育ニーズは高まっています。
2. 認定区分を超えたマーケティングの必要性
従来の幼稚園、保育所といった枠組みを超え、0歳児から就学前まで一貫した教育・保育を提供する施設へのニーズが高まると考えられます。これに伴い、認定区分を意識せず、0歳児からのマーケティング活動が重要となります。
3. 認定こども園移行の困難化とM&Aの増加
待機児童の減少に伴い、幼稚園の認定こども園移行はさらに難しくなると予想されます。また、経営難に陥る園も増加し、業界内でのM&Aが活発化すると考えられます。
4. 財務情報公開の義務化と経営の透明化
2025年度からは、認定こども園と幼稚園においても財務情報の公開が義務付けられます。 これにより、保護者からの財務状況に対する関心が高まり、より透明性の高い経営が求められるようになります。
5. 人材不足の深刻化と働き方改革の必要性
少子化による人材不足は、幼保業界においても深刻化しています。優秀な人材を確保し、定着させるためには、働き方改革を推進し、魅力的な職場環境を整備することが重要となります。
2025年に生き残るために:戦略的「拡大」or「縮小」の決断
2025年、認定こども園・幼稚園が生き残りを図るためには、「戦略的拡大」か「戦略的縮小」のどちらかの方向性を明確に決断する必要があります。
1. 戦略的「拡大」
総合子ども子育て支援拠点化を視野に入れ、地域の子育て支援のニーズを包括的に満たす体制を構築する。
事業規模の拡大を目指し、中期経営計画を策定し、組織体制を見直す。
人材育成に注力し、質の高い保育・教育を提供できる体制を強化する。
2. 戦略的「縮小」
市場規模に合わせた定員設定を行い、収支のバランスを図る。
経営数値管理体制を強化し、財務基盤の安定化を図る。
業務の効率化を推進し、限られた人員で質の高い保育・教育を提供できる体制を構築する。
具体的な取り組み:広報戦略とマーケティング強化
戦略的「拡大」・「縮小」の方向性を決定したら、それに合わせた具体的な取り組みを進めていく必要があります。特に、広報戦略とマーケティング強化は、園児募集において非常に重要です。
1. 消費者行動モデル「DECAX」に基づいた広報活動
消費者行動モデル「DECAX」とは、Discovery(発見)、Engage(関係構築)、Check(確認)、Action(行動・購入)、Experience(体験)という5つの段階を踏まえ、消費者の行動を促すマーケティング手法です。
幼保園の広報活動においても、DECAXモデルを意識することで、より効果的に園児募集につなげることが可能となります。
2. オンラインとオフラインを組み合わせた多角的な広報戦略
従来のチラシやポスターなどのオフライン施策に加え、ホームページやSNSなどのオンライン施策を積極的に活用することで、より多くの潜在顧客にアプローチすることが可能となります。
特に、SNS広告は、特定のエリアや属性のユーザーに絞って広告配信できるため、効率的にターゲットにリーチすることができます。 また、ランディングページを用意することで、ホームページでは伝えきれない園の魅力や情報を詳しく伝えることができます。
3. 個別見学会の充実
個別見学会は、園の雰囲気や保育内容を実際に体験してもらう貴重な機会です。 見学会の内容を充実させることで、入園希望者の満足度を高め、入園決定率の向上につなげることができます。
レポートダウンロードのお勧め
より詳細な情報や具体的な事例については、船井総合研究所が発行する「【認定こども園・幼稚園】2025 時流予測レポート」をご覧ください。本レポートでは、2025年の認定こども園・幼稚園業界の展望、成功事例、具体的な戦略などを詳しく解説しています。
今すぐダウンロードして、自園の未来を創造しましょう。
幼保業界を取り巻く環境は、今後も大きく変化していくことが予想されます。しかし、変化を恐れず、積極的に対応していくことで、必ず未来を切り開くことができるはずです。
船井総合研究所は、全国の認定こども園・幼稚園を運営する皆様をサポートさせていただきます。
経営に関するお悩みやご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。