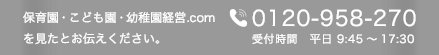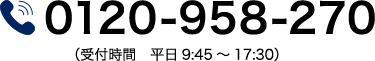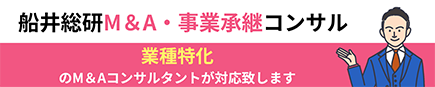いつも コラムをご覧いただきありがとうございます。
船井総合研究所 子育て支援部の児玉です。
「卒園児の保護者から『預け先の学童がない』『学童が18時で閉まってしまう』といった切実な声が届く」
「小学校進学後の方が、働き方の制限が出る職員が多く、遅番勤務が不足している」
「保育園を卒園した後も、地域の子どもたちのためにできることをしたい」
保育園・幼稚園・認定こども園を経営される中で、こうした「小1の壁」問題に心を痛めている方も多いのではないでしょうか。
保育の待機児童問題が解消に向かう一方で、この「学童保育」の待機児童問題は、今や地域社会全体、そして日本中の企業にとっての深刻な経営課題となっています。
本コラムでは、政治の世界でも注目され始めた「企業主導型学童」というキーワードをフックに、学童保育の現状と、保育事業者が参入することで実現できる「地域ニーズへの貢献」「切れ目ない支援」の可能性について解説します。
総裁選でも注目!「企業主導型学童」とは何か
2025年、女性初の内閣総理大臣に選ばれた高市早苗氏が、自民党総裁選の公約として「『企業主導型学童』を創設します」と掲げたことが大きな注目を集めました。
「企業主導型学童」という単語自体、この総裁選が初出とも言える新しい言葉です。このアイデアのベースとなっているのは、皆様ご存知の「企業主導型保育事業」であると思われます。
平成28年(2016年)に始まった企業主導型保育事業は、待機児童解消の切り札として急速に拡大しました。令和3年度(2021年度)までに定員11万人分を確保し、現在は新規募集を終了したものの、令和7年(2025年)7月現在では4,280施設・定員約10万人分が確保されています。
この事業の貢献は大きく、全国の待機児童数は平成29年(2017年)の26,081人から、令和7年(2025年)4月には2,254人と、10分の1以下まで激減しました。
これを「学童保育」にも応用し、地域の社会課題を解決しようというのが、「企業主導型学童」の基本的な考え方であろうと考えられます。
なぜ今、学童保育が「社会課題」「経営課題」なのか?
企業主導型保育事業が保育の待機児童問題を解決しつつある今、なぜ「学童保育」なのでしょうか。それは、「小1の壁」が、地域で働く保護者と、彼らを雇用する一般企業にとって、非常に高く厚い壁となっているからです。
厚生労働省の発表(令和6年・2024年実施状況)によると、放課後児童クラブ(学童保育)の登録児童数は1,519,652人と前年から約6.2万人増加しました。一方で、利用できなかった児童数(待機児童)は17,686人と、前年より1,410人増加しています。
保育の待機児童が解決してきたからこそ、この「学童の待機児童」問題が、働く保護者にとっての新たな、そしてより深刻な壁として立ちはだかっているのです。
問題は待機児童の数だけではありません。運良く学童に入れたとしても、開所時間の問題があります。
地域の放課後児童クラブは17時や18時に閉所することが多く、延長保育を利用すれば19時や20時まで預けられた保育園時代と比べ、預かり時間に大きなギャップが生まれます。
結果として、「保育園時代はフルタイムで働けていた保護者が、子どもが小学校に上がった途端、働き方を変えざるを得ない(時短勤務・離職)」という事態が発生します。
これは、貴園の職員だけの問題ではなく、地域で働くあらゆる保護者にとっての課題です。そして、従業員の就労継続を困難にさせるこの問題は、人手不足に悩む多くの一般企業にとって、人材確保や定着に直結する深刻な「経営課題」となっているのです。
「企業主導型学童」の構想は、こうした社会課題を解決する可能性を秘めていると考えられます。
一部の大手病院では、すでに病院内に学童保育を設置し、夜間勤務を行う看護師のお子さんの預かり場所を自力で確保している事例もあります。企業主導型保育事業と同様に、開所曜日や時間を柔軟に設計できる学童保育が地域に増えれば、安心して働き続けられる保護者が増え、企業の人材不足解消にも貢献できるでしょう。
「民間学童保育参入」を後押しする各自治体の最新動向
「企業主導型学童」という国の制度はまだ構想段階だと思われますが、自治体レベルでは、民間の力を活用して学童保育を拡充しようとする動きがすでに始まっています。
事例1:東京都「東京都認証学童クラブ」事業
東京都は、令和7年(2025年)4月に「東京都認証学童クラブ」事業を開始しました。これは、既存の幼稚園・保育園・認定こども園が、空き教室や園庭・園舎を活用して学童クラブを運営することを後押しするものです。
必要な人件費や、送迎バス代等の運営経費に対する補助メニューを充実させており、都内の幼稚園等には積極的に周知するチラシが配布されています。
事例2:松山市「松山市放課後児童健全育成事業費補助金」
愛媛県松山市でも、令和6年度(2024年度)から「松山市放課後児童健全育成事業費補助金」を開始しました。これにより、民間児童クラブへの事業費補助がスタートしています。
このように、自治体が独自に民間参入を促す制度を整備する動きは、全国で広がりつつあります。
補助金がなくても可能?「習い事付き学童」という事業モデル
「自分の自治体には、まだ民間学童への補助制度がない」
そういった地域も残念ながら多く存在します。しかし、補助金がない場合でも、事業化の道はあります。 それは、貴園が持つ「保育・教育の特色」を活かす方法です。
例えば、幼稚園や認定こども園で実施している「課外活動」や「設定保育」のノウハウを活かし、「習い事付きの民間学童」として運営し、保護者からその付加価値に見合う利用料を受け取るモデルです。
これらは、単なる「預かり」のニーズだけでなく、「放課後の時間を有効に使わせたい」という保護者の教育ニーズも満たすことができます。結果として、補助金がなくても事業性を保ちつつ、地域の「小1の壁」解消に貢献することが可能になります。
「学童保育」は、地域と卒園児のための「切れ目ない支援」の一つ
「学童保育」の未来は、未知数な部分も多いですが、確実に言えることは、社会的なニーズが非常に高まっている領域であるということです。貴園が持つ「施設(空き教室など)」「人材」「保育・教育ノウハウ」「地域からの信頼」は、学童保育事業を始める上で非常に大きなアドバンテージとなります。
何よりも、地域の課題に応え、卒園児とその保護者を小学校入学後も継続的にサポートする「切れ目ない支援」を実現することは、貴園の地域における存在価値を、より一層高めることに繋がるはずです。「学童保育」への参入を、地域貢献と安定経営の次の一手として、検討してみてはいかがでしょうか。
船井総合研究所では、こうした新たな事業展開に関する情報発信や、経営コンサルティングを継続的に行っています。
「自分の地域でも参入のチャンスはあるだろうか?」
「具体的な事業モデルや収支シミュレーションを知りたい」
「自治体の補助金情報について詳しく聞きたい」
このような疑問やお悩みをお持ちの経営者様・理事長様・園長様は、ぜひ船井総合研究所の無料個別経営相談をご活用ください。
保育・教育業界を専門とするコンサルタントが、貴園の状況や地域特性を踏まえ、学童保育参入の可能性について具体的なアドバイスをさせていただきます。
まずは、下記よりお気軽にお問い合わせください。
無料経営相談のご案内