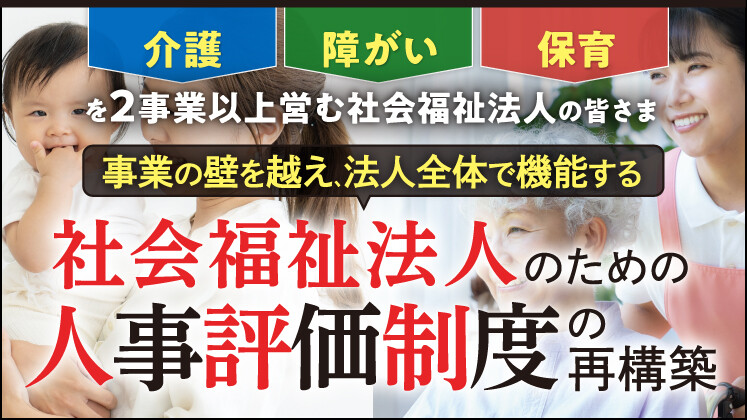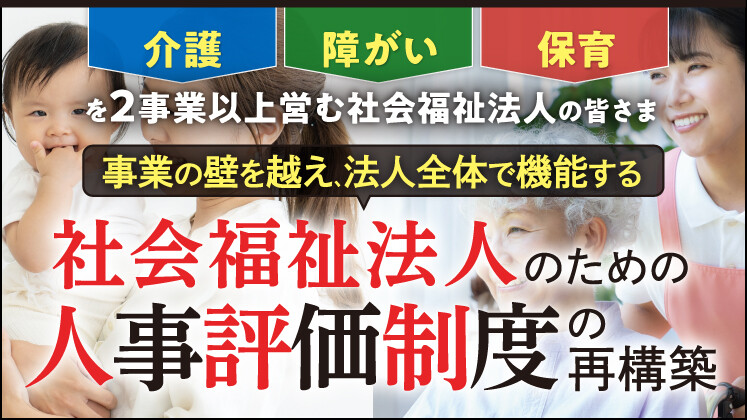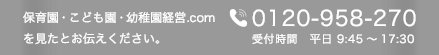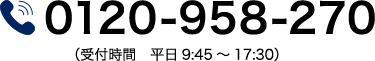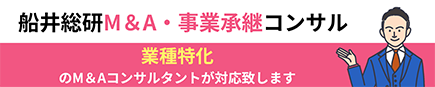いつも コラムをご覧いただきありがとうございます。
船井総合研究所 子育て支援部の児玉です。
2025年は、経営情報の見える化、そして処遇改善等加算の一本化など、保育園・幼稚園・認定こども園業界にとって重要な制度変更が相次いだ激動の1年でした。日々の業務に加え、これらの変化への対応に追われ、「とりあえず何とか形にした」という法人様も少なくないのではないでしょうか。
しかし、これらの変化を単なる「守り」の対応、つまり制度に合わせた事務作業で終わらせるか。それとも、職員の働きがいと定着を促進する「攻め」の武器へと転換できるか。その差が、2026年度以降の法人経営を大きく左右する分岐点となります。
なぜ今、保育園・幼稚園・認定こども園に「人事評価制度」が不可欠なのか
今回の制度変更で、特に重要度を増しているのが「人事評価制度」です。
「経営情報の見える化」では、職員に対して「〇年目でどの程度の給与がもらえるのか」というモデル給与の提示が求められるようになりました。また、「処遇改善等加算の一本化」に伴う配分ルールの策定や監査においても、なぜその職員にその金額が配分されるのか、客観的な根拠がこれまで以上に厳しく問われるケースが増えています。
つまり、給与・賞与の支給基準、昇格の判断基準などを明確に定め、それを職員に示し、納得感を得ることが、制度上も、そして職員の定着という観点からも不可欠となっているのです。その土台となるのが、客観的で公平な人事評価制度に他なりません。
その評価制度、機能していますか?「評価制度」機能不全度チェックリスト
「評価制度なら、うちの園にも既にある」とお考えの経営者様もいらっしゃるかもしれません。しかし、その制度は本当に機能しているでしょうか?もし、下記の項目に一つでも当てはまるなら、制度が形骸化している危険なサインです。
✅ 職員は評価の時しか評価項目を思い出さず、普段の行動に変化がない。
✅ 収入はほとんど変わらないのに職員の昇給が続くので、人件費を圧迫している。
✅ 課題の多いパート職員にこそ必要なはずが、評価制度は正社員のみで問題が放置されている。
✅ 「責任が増えるのに給料はあまり変わらない」と、職員が主任やリーダーへの昇格を嫌がる。
✅ 園児募集に協力してほしいのに、「それは私たちの仕事じゃない」と非協力的な職員がいる。
✅ 処遇改善加算の配分がどんぶり勘定で、職員のモチベーション向上に繋がっている実感がない。
✅ 評価項目が多すぎて、園長が一人ひとりを評価しきれず、負担が限界に来ている。
✅ 指導が必要な課題職員も、今の評価制度上 定期昇給できてしまう。
✅ 半年に1回の評価面談が、ただの「流れ作業」になっている。
✅ 評価者によって評価が甘い・厳しいがあり、職員から不満の声が出ている。
✅ 職員への結果のフィードバックが怖くて、正直に改善点を伝えられていない。
✅ フィードバックはしているが、職員の改善や成長に繋がっている実感がない。
✅ 「個人目標」を設定させているが、何をどう評価すれば良いか不明な目標が多く、形骸化している。
これらの「機能不全」を放置することは、職員の不満を増大させ、離職率の悪化や保育の質の低下に直結する、非常に危険な状態と言えます。
貴園はどっち?人事評価制度の2つの型
「では、どのような評価制度を導入すれば良いのか?」その答えは、一つではありません。評価制度は、法人の理念や成長段階、目指す方向性によって最適な形が異なります。また、一度導入したら終わりではなく、組織の状態に合わせて継続的に見直していくことが成功の鍵です。
船井総合研究所では、法人の状況に合わせて、大きく2つのモデルをご提案しています。
モデル1:理想追求型(全員成長モデル)
法人の理念が隅々まで浸透しており、全職員が同じ方向を向いて保育に取り組んでいる。職員間の価値観やスキルの差が比較的小さい――。このような組織状態の法人様には、全職員の自己成長を促す評価制度が機能しやすいでしょう。
例えば、「個人目標管理制度」を導入し、一人ひとりが自身の成長目標を設定し、その達成度を評価に反映させることで、主体的な成長と法人への貢献意欲を高めることができます。
モデル2:現実対応型(二階層モデル)
一方で、下記のような法人様も多いのではないでしょうか。
・組織の拡大期で、次々と新しい職員が入職している
・まずは職員の負担を小さく、気軽に評価制度を導入したい
・離職率の改善や、課題職員の是正を優先したい
このような場合は、「キャリアアップを望む職員」と「現場で活躍し続けることを希望する職員」で、求める役割と評価の仕組みを分ける「二階層モデル」が有効です。
「スペシャリスト」育成の落とし穴と、あるべき姿
職員の中には、「管理職ではなく、現場のスペシャリストとして活躍し続けたいし、そこを評価して給与にも反映してほしい」という声もあるかもしれません。専門性を高めること自体はとても素晴らしいのですが、ここで一つ注意が必要です。
管理職を経験していない「スペシャリスト」は、時に視野が狭くなり、自分のやり方に固執して若手を潰してしまったり、園の方針に反発したりするリスクを孕んでいます。
スペシャリストを目指すこと自体は悪くないですが、そういった人材こそ、一度、主任や園長といった管理職として組織全体の視点を持ち、視野を広げた上で、その経験を現場や法人全体に還元してほしい、というメッセージを伝えることも重要となります。
まとめ:評価制度の見直しで、2026年度の飛躍を
2025年の制度変更は、貴園の人事評価制度を抜本的に見直す絶好の機会です。
場当たり的な対応で終わらせるのではなく、この機会に自法人の理念や実態に合った評価制度を構築・再整備することが、職員の定着率とモチベーションを向上させ、地域で選ばれる園になるための確かな一歩となります。
まずは、先ほどの「チェックリスト」を使い、自園の現状を客観的に把握することから始めてみてはいかがでしょうか。
「自園に合った評価制度がわからない」
「制度の導入や見直しを、何から手をつければ良いか迷っている」
そのような経営者の皆様は、ぜひ一度、私たち船井総合研究所にご相談ください。これまで全国の保育園・幼稚園・認定こども園様の経営をサポートしてきた専門コンサルタントが、貴園の課題に合わせた最適な評価制度の設計から導入、そして運用定着までを伴走支援させていただきます。
まずは、お気軽に無料の経営相談をご活用ください。
介護・障がい・保育 経営課題を解決する人事評価制度セミナー