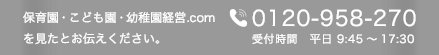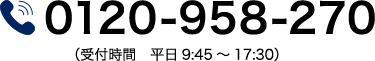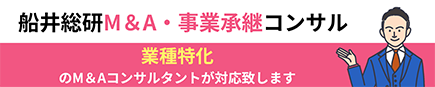経営者が頑張りすぎていませんか?代表の業務抱え込みすぎ問題を考える
- テーマ:
- 働き方改革
いつもお読みいただきありがとうございます。
株式会社船井総合研究所の永田屋でございます。
今日は保育業界における「代表の業務抱えすぎ問題」についてお伝えしたいと思います。
突然ですが、あなたは今、「なんでも自分でやった方が早い」と感じていませんか?
園児の募集から職員の採用、行政対応、日々のトラブル対応まで、気づけば経営者であるあなたがほとんどの業務を抱え込んでしまっている…そんな状況、心当たりはありませんでしょうか。
このような状況は、法人規模のそれほど大きくない事業者の多い保育業界ではよく見られる光景です。しかし、その状態は経営者自身が疲弊するだけでなく、本来取り組むべき経営業務がおろそかになり、事業の成長を鈍らせてしまう原因にもなりかねないというリスクがあります。
今回は、そんな「代表の業務抱え込みすぎ問題」を解決するためのヒントを、「仕組み」と「心持ち」という2つの観点から考えていきたいと思います。
任せられない・頼れない組織
保育事業者の多くは、代表の下に園長先生や主任の先生方がいます。彼らは保育のプロフェッショナルですが、「経営」の目線では経験が乏しい方も少なくありません。
そのため、園児の募集や職員の採用といった目先の施策から、新たな事業展開や事業計画策定といった中長期的な施策まで、経営に関わることを相談したり、頼ったりすることができず、代表が一人で抱え込んでいるケースが多く見られます。当然これに加えて、突発的なトラブルやクレーム、職員のケア、行政対応など、予測しにくい業務も多数存在します。
経営者は「意思決定業」だと言われます。法人を推進するために一つひとつの意思決定をすることは、経営者として重要な仕事です。しかし、それに付随する事務作業、例えば各種書類の作成、外部業者とのやり取り、労務管理など、やり方さえわかれば経営者でなくてもできる仕事まで抱え込んでいませんでしょうか。
法人ごとの様々な事情から、すぐに業務を手放すのは難しいケースは多いかと思います。しかし、それらの付随業務のせいで本来の「経営者としての仕事」が圧迫されているのだとすれば、それは事業の推進力が弱まっている状態に陥っているかもしれません。
仕事を任せる「仕組み」
事業運営に関わる多くの情報は、当然ですが経営者のもとに集まりやすいため、「自分でやってしまった方が早い」と感じることは多いでしょう。確かにその瞬間は手間も時間もかからないかもしれません。しかし、それを続けていくと、経営者の元にどんどん業務が集まってきてしまいます。
優秀な右腕がいれば負担は少ないですが、多くの法人では現場特化型の人材が大半で、高いレベルで事務業務をこなせる人材がいないのが現状かと思います。優秀な幹部を探し、育てるアプローチも重要ですが、それなりに長い時間の投資が必要となり、一朝一夕にはいかないのも事実です。その中で少しでも改善を図っていくのであれば、まずは抱えている業務を棚卸しし、それを任せられる仕組み作りが重要です。
今抱えている業務をすべて書き出してみると、必ず経営者でなくてもよい仕事が見つかるはずです。そのような業務から何を手放していくかを見極め、手順書のような形でまとめておくことが考えられます。「言わなくてもわかる」というレベルはできれば理想ですが、その実現が難しいため、とりあえず「見れば最低限わかる」ものを作ることが有効です。これにより、任せる側・任される側の双方のコミュニケーションコストやストレスを軽減した上で、業務を移譲できます。
また、保育業界は人材の入れ替わりが多い業界です。手順書を整備しておけば、作業を担う方が入れ替わったとしても、早期に業務の理解と実施が可能になり、入退職に伴う負担の軽減にもつながります。手順書は書面でもデータファイルでも、場合によっては短い動画でも良いかもしれません。このような仕組み化のアプローチを整えることで、経営者としての仕事に注力できるようになります。
仕事を任せる「心持ち」
もう一つの問題として、心情的に任せられないという経営者も多いです。経営者は法人の最終責任者であり、誰かに任せた上での失敗も、最終的にはあなたの責任となります。そのため、法人の根幹を揺るがすような失敗は避けなければなりません。
一方で、さまざまな小さな失敗を経験しないことには、人は成長しないのも事実です。経営者が全てを巻き取り、失敗しないような環境を作りすぎると、「上が判断してくれる」「深く考えなくても良い」という風土ができてしまう側面もあります。
これは、子どもの保育においても同じです。一切失敗しないように整えられた環境で育つと、失敗に対する耐性が弱く、また失敗に向き合って学ぼうとする姿勢が育まれにくいのは、保育事業に携わる皆様であればイメージしやすいかもしれません。
将来的な幹部人材を育てていくためにも、短期的な失敗を飲み込み、フォローし、前向きな改善につなげていく「度量」や「勇気」といったものが、時には必要となる場面があります。
代表の業務抱えすぎ問題は、すぐに解消できるものではありません。会社としての仕組みを整え、場合によってはその風土や経営者自身のマインドを変えていく必要もあります。このメルマガを読んで、「うちの園ではどうすればいいんだろう?」と具体的なアクションに悩んだ方は、ぜひお気軽にご相談ください。あなたの園に合わせた最適な方法を考えるお手伝いをさせていただきます。
このメルマガが、より多くの経営者が本来の仕事に注力するためのヒントになっていれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。