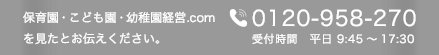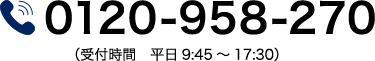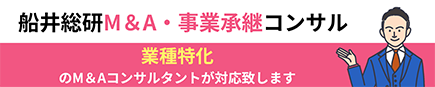皆様
いつも保育園経営.com のコラムをご愛読いただきましてありがとうございます。
船井総合研究所 子育て支援部の菅野 瑛大(かんの あきひろ)です。
多くの法人が抱える「任せられる人がいない」問題
少子化の加速、相次ぐ制度変更、そして地域における競争の激化——。保育業界を取り巻く環境が不確実性を増す中、多くの経営者が「事業の成長」以前に、まず「経営の安定化」という課題に直面しています。
日々の保育品質を守る「現場責任者」はいても、変化の波を乗りこなし、組織の基盤を固める「経営幹部」が育っていない。この課題は、法人の存続そのものを揺がしかねません。
本コラムでは、事業拡大という「攻め」の発想から一度視点を変え、いかにして組織の「守りを固め」、変化にしなやかに対応できる「多機能化」の土台を築くか、という観点から、これからの時代に不可欠な幹部育成の新基軸をお示しします。
安定の基盤:「園運営」と「園経営」の役割分担
組織の安定化を考える上で、まず「マネジメント」という言葉の解像度を上げる必要があります。現場リーダーの多くは、質の高い「園運営」のプロフェッショナルです。
しかし、真の安定はそれだけでは築けません。「園経営」という、もう一つの重要な視点が不可欠です。
◎園運営(日々の守り)
→日々の教育保育の品質担保、職員の配置管理、安全管理など、園の日常を高いレベルで維持すること。これは組織の土台であり、安定に不可欠な「守り」のマネジメントです。
◎園経営(未来を固める)
→収支や人員計画の管理、職員の定着・育成戦略、制度変更への対応、新たな事業(多機能化)の検討など、中長期的な視点で組織の基盤を固めること。
現場が「園運営」に集中できる環境は理想です。しかし、リーダー層がその視点に留まっていては、職員の離職や制度変更といった外部からの揺ぶりに対して組織はあまりにも脆弱です。変化に対応し、組織の基盤を「固める」ためには、園長や主任層に「園経営」の視点を持ってもらうことが絶対条件となります。
「下限品質」と「上限品質」の明確化もポイントです。職員育成において、「このくらいはできてほしい」「普通だったらこうだろう」といった曖昧な基準では、具体的な成長を促すことはできません。法人として「入職時に達成してほしい最低限のレベル」を「下限品質」として明確に定義し、さらに「法人にとって利益を生む理想的な水準」を「上限品質」として示すことが重要です。これは「できる/できない」という減点方式的な評価ではなく、職員がどこに向かって成長すべきかの道筋を示す「加点方式」の視点へと転換を促します。
安定化への二つの道筋:あなたの法人はどちらを目指すか
実は、保育サービスは一般ユーザーからでは違いが分かりにくい状態(=コモディティ化)が進んでいます。
こうした中で、経営を安定させる戦略は大きく二つに分かれます。そして、その戦略によって育成すべき幹部のタイプも変わってきます。
1. 理念を中核とした「ブランド安定化」
独自の保育哲学や理念を強力なブランドとして確立し、それに共感する保護者や職員の強いロイヤリティを醸成する。価格や利便性だけで選ばれない、強固なファンコミュニティを築くことで、外部環境の変化に左右されにくい安定した経営を目指します。
確立されたブランドへの信頼を基盤に、「こども誰でも通園制度」の活用や、卒園児向けプログラム、保護者支援サービスなど、新たな価値提供(多機能化)へとスムーズに展開できます。
この時に求められる幹部増は、理念の伝道師です。法人の哲学を深く理解し、それを職員や保護者に魅力的に伝え、共感を育むことができるコミュニティビルダーを育成していくことが重要です。
2. 仕組みを中核とした「組織安定化」
業務の標準化、効率的な情報共有、公平な人事評価制度といった「仕組み」を徹底的に構築する。特定のスター職員に依存しない、誰がやっても一定の質が担保される堅牢な組織を作り上げることで、安定性を確保します。
整備された業務フローやシステムを基盤に、新たな事業を着実に組織へ統合していきます。戦略的なDX推進により、職員の負担を増やさずにサービスの多角化を実現します。
この際に求められる幹部増は、システムの構築者です。業務プロセスを分析・改善し、テクノロジーを活用して組織全体の生産性を向上させることができるオペレーションの専門家として、“業務”をマネジメントしていくことで、運営体制が強化され、結果的によりよい園経営につながっていきます。
どちらの戦略が優れているというわけではありません。
重要なのは、自法人がどちらの道で「安定」を目指すのかを経営陣が明確に定め、その戦略に合致した幹部を計画的に育成することです。
もっと言えば、双方の仕掛けを実現できることが、最も望ましいでしょう。
安定経営を担う幹部を育てる3つのステップ
1.意識改革
「職種」から「職業」へ 幹部への成長は、自らを単なる「保育士」という専門職(職種)ではなく、法人の一員(職業)として認識することから始まります。法人の存続と安定に貢献することが自らの役割である、という当事者意識(組織人マインド)の醸成がすべての土台です。
2.現状の見える化
非効率をコストとして認識する 「あの書類どこだっけ?」―この何気ない一言が、法人全体で年間数百万円もの損失を生んでいる可能性を認識できているでしょうか。経営の安定化を目指す幹部には、こうした目に見えない非効率を「感覚的な手間」ではなく「具体的な経営コスト」として捉え、DXなどを通じて改善する視点が求められます。
3.未来へのアンテナ
制度変更を「機会」として捉える 処遇改善加算の一本化や経営情報の公開義務化など、今後の制度変更は避けられません。これを「やらされ仕事」と捉えるか、「人事制度を再構築し、職員の定着率を高める好機」と捉えるかで、組織の未来は大きく変わります。変化を予測し、事前準備を促すこと、これもまた安定経営を担う幹部の重要な役割です。
育成には経営陣による「地ならし」が必要
「現場のリーダーにもっと経営視点を」と願うものの、具体的に何から手をつければよいか、悩まれる経営者様も多いのではないでしょうか。大切なのは、この課題を「現場任せ」にしないことです。
幹部育成の成否は、実は職員の努力以前に、経営陣がどれだけ丁寧な「地ならし」を行えるかにかかっています。
もちろん、職員に「自分で考えて動いてほしい」という経営者の皆様の想いはもっともです。
しかし、改めて、制度理解(既存の制度だけではなく新たに出てくるパッケージも含めて)を深めていき、保育事業戦略(事業だけではなく組織戦略や働き方改革なども統合的に考えて)を経営陣が羅針盤としてこの「設計図」を明確に示して初めて、現場のリーダーたちは安心して「園運営」の枠を超え、「園経営」という新たな領域に一歩踏み入れることができます。
変化の時代における真の安定とは、現状維持ではなく、変化に対応し続けられる強い組織を築くこと。そのための地ならしこそ、経営者に課せられた最も重要な役割であり、その中心には経営視点を持った幹部の存在が不可欠なのです。
時流・業界動向
採用・育成
処遇改善等加算
企業主導型保育事業向け 処遇改善等加算セミナー2025 のご案内
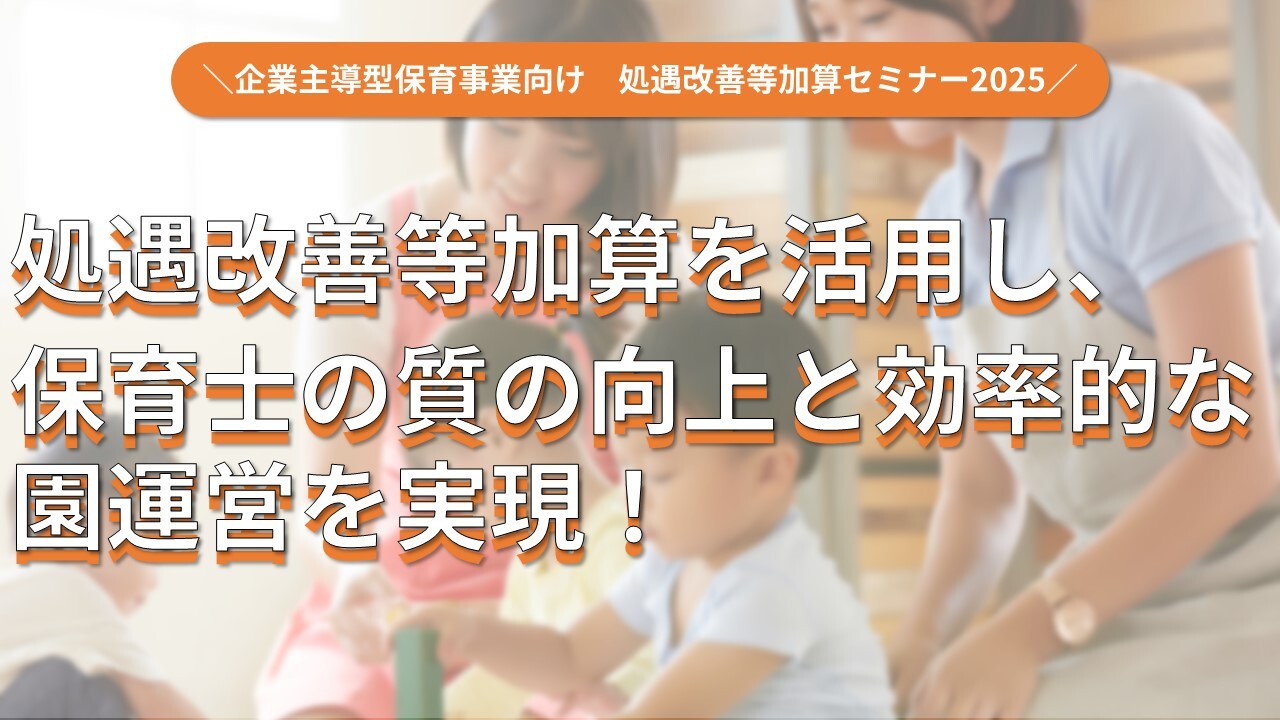
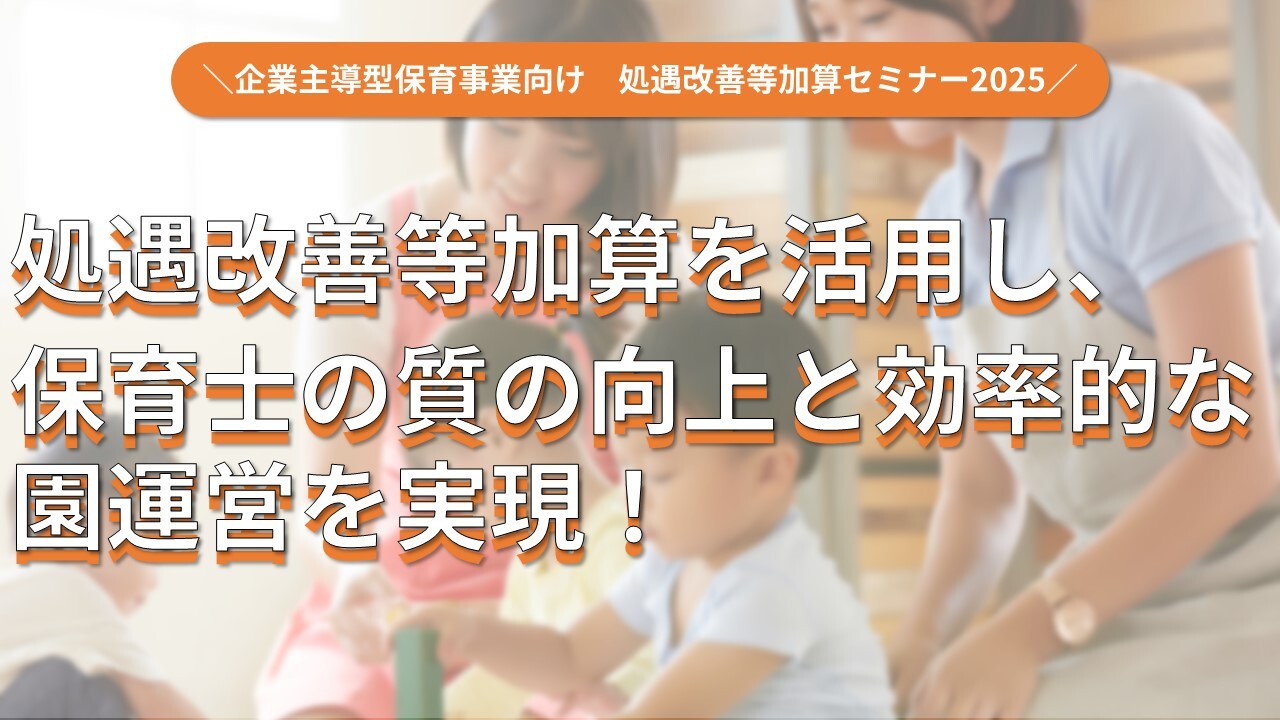
本コラムでは、経営の安定化に向けた幹部育成の考え方について解説しました。職員の定着と育成は、安定経営の根幹をなす「園経営」の重要テーマです。その基盤となる職員の処遇を改善し、監査にも対応できる盤石な体制を築くための具体的な手法について、セミナーのご紹介です。
<下記に当てはまる方はぜひご参加ください! >
☑ 事業計画申請で新たに処遇改善等加算を申請した方
☑ 来年度以降処遇改善等加算の取得を検討している方
☑ 正しい賃金改善計画が立てられているか不安な方
☑ 職員のモチベーションアップにつながる改善をしたいと考えている方
☑ 過去に処遇改善等加算関係で監査の指摘を受けた方
☑ 毎年、いくら処遇改善等加算の原資として分配できるのかが良くわからない方
<開催日程>
全日オンライン (Zoom) 開催
2025年 9月19日(金)、9月22日(月)
2025年 9月24日(水)、9月30日(火)
<開催時間>
全日程13:00~15:00 (ログイン開始12:30~)
<参加費用>
・一般価格 10,000円(税込11,000円)/一名様
・会員価格 8,000円(税込8,800円)/一名様