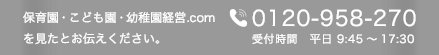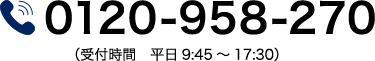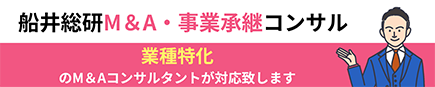【企業主導型保育事業】処遇改善等加算の「公平な」配分計画とは?
船井総合研究所 子育て支援部の小島です。
いつも保育園経営.comのコラムをお読みいただきありがとうございます。
本日は企業主導型保育事業における処遇改善等加算の配分事例についてお伝えします。
企業主導型保育事業においても、処遇改善等加算と聞くと、「職員の賃金を上げるためのもの」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。もちろん、職員の賃金改善は最も重要な目的の1つです。しかし、この加算はただ給料を上げるだけでなく、「長く働きたい」と思える職場環境を構築し、ひいては質の高い保育を実現するための大切な財源となっています。
加算金の配分方法を少し工夫するだけで、職員のモチベーションが上がり、キャリアパスが明確になり、園全体の運営がスムーズになる可能性があります。そこで、本日は企業主導型保育事業での処遇改善等加算の具体的な配分事例を、処遇改善等加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3つの加算ごとに分けてご紹介します。
処遇改善等加算Ⅰ:柔軟な配分が可能!
処遇改善等加算Ⅰは、職員の平均経験年数やキャリアアップへの取り組みに応じた人件費の加算であり、3つの処遇改善等加算の中で最も支給方法の自由度が高いことが特徴です。この柔軟性を活かすことで、園の運営方針や職員の働き方に応じた、多様な配分が可能となります。
ここでは処遇改善等加算Ⅰの配分事例を3点、お伝えいたします。
事例①
「年間の加算額が確定してから、勤務時間や能力評価に基づき、一時金として一括で支給する」という方法です。この方法の最大のメリットは、法人が支給額を事前に把握しやすいため、計画的に加算を運用できる点です。また、職員の努力や成果を評価に反映させやすいため、納得感のある支給に繋がりやすいでしょう。
事例②
等級や号棒といった園の給与制度と連動させて、毎月の給与に上乗せして配分する方法です。等級が上がるごとに加算額が増える仕組みにすることで、職員は将来のキャリアを具体的にイメージしやすくなります。
事例③
正規職員、時短職員、非常勤職員といった勤務形態ごとに割合を設定して毎月配分する方法です。これにより、多様な働き方をする職員にも公平に処遇改善等加算Ⅰの原資を配分することが可能です。
このように、処遇改善等加算Ⅰは、園の目標や職員の状況に合わせて、様々な形で活用できます。園の課題を解決するための一手として、ぜひご検討ください。
処遇改善等加算Ⅱ・Ⅲ:キャリアパスを明確化
次に、処遇改善等加算ⅡとⅢの活用方法についてお伝えします。これらの加算は、加算額の算定方法や配分ルールに一定の条件がありますが、工夫次第で職員の意欲を高め、やる気のある職員が長く働き続けられる職場環境を作ることが可能です。
処遇改善等加算Ⅱ
処遇改善等加算Ⅱは、技能や経験を積んだ職員に対する追加的な人件費の加算です。
事例
「園内で役職ごとの新たな業務を定義し、従事する職員に支給する」
例えば、「専門リーダー」や「職務分野別リーダー」といった役職に、人材採用や保育カリキュラム開発などの具体的な業務を割り当て、増えた役割に対する対価として処遇改善等加算Ⅱを支給することで、。職員間の不公平感を払しょくすることができます。
また、設定したリーダーへの任命要件を明確化することで自身のキャリアを明確に描きやすくなり、自律的な成長を促すことができます。
具体的な配分事例としては、「副主任1名に4万円、職務分野別リーダー等に5千円を配分し、残りを主任保育士等に4万円未満で配分する」という事例や、等級や役職に応じて傾斜配分する事例があります。ただし、加算Ⅱは研修修了要件がある点に注意が必要です。キャリアアップ研修修了書記載月の翌月(修了日が1日の場合は当月)からしか支給ができないため、計画的に研修を修了しておくことが求められます。
処遇改善等加算Ⅲ
処遇改善等加算Ⅲは、職員の賃金の継続的な引上げを目的とした加算です。この加算の改善ルールの特徴は、改善額の3分の2以上を基本給または毎月支払われる手当の引き上げに充てる必要がある点です。
事例①
「処遇改善等加算Ⅰ、Ⅱの対象にできない職員を中心に配分する」
処遇改善等加算Ⅲの対象職員は施設に勤務する職員全般にわたるため、処遇改善等加算ⅠやⅡの対象にできない職員(病児保育看護師、連携推進員など)を中心に配分する事例も有効です。
事例②
「常勤職員を基準とし、労働時間などで配分する」
この配分事例では、園で働くすべての職員を対象とすることで賃金の継続的な引き上げという本来の目的を活かすことができます。他にも、常勤職員だけでなく、準正規職員、時短職員、非常勤職員など、幅広い職員に配分することで、多様な働き方に対応して公平に賃金改善に充てることが可能です。
処遇改善等加算ⅡとⅢを効果的に配分することで、継続的な賃金改善と、役職ごとの役割に応じたキャリアパスの構築に活用することができます。
まとめ
ここまで、処遇改善等加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの具体的な配分事例をお伝えしました。処遇改善等加算は、単なる賃金改善に留まらず、職員のキャリアパス構築やモチベーション向上、ひいては園全体の保育の質向上と安定的な運営に繋がる重要な加算です。
しかし、注意点もあります。例えば、監査では加算の配分方法が給与規定などの明確な根拠に基づいているか、また職員に適切に周知されているかといった点が確認されます。さらに、処遇改善等加算を支給されていることを職員が理解できていないケースや、割増賃金の算定基礎に含んでおらず残業代の未払いになっているケースなど、専門的な労務監査で指摘を受けることも少なくありません。
加算を最大限に活用し、職員の不公平感をなくすためには、加算の要件や新たな役職の業務・役割を明確にし、職員に周知することが不可欠です。ぜひ、今回の内容を参考に、園の状況に合わせた最適な配分計画を策定し、園の成長に繋げていきましょう。このコラムがその一助となれば幸いです。
・処遇改善等加算
・収支改善
・企業主導型保育
・セミナー・研究会のご案内
・時流・業界動向
企業主導型保育事業向け 処遇改善等加算セミナー2025
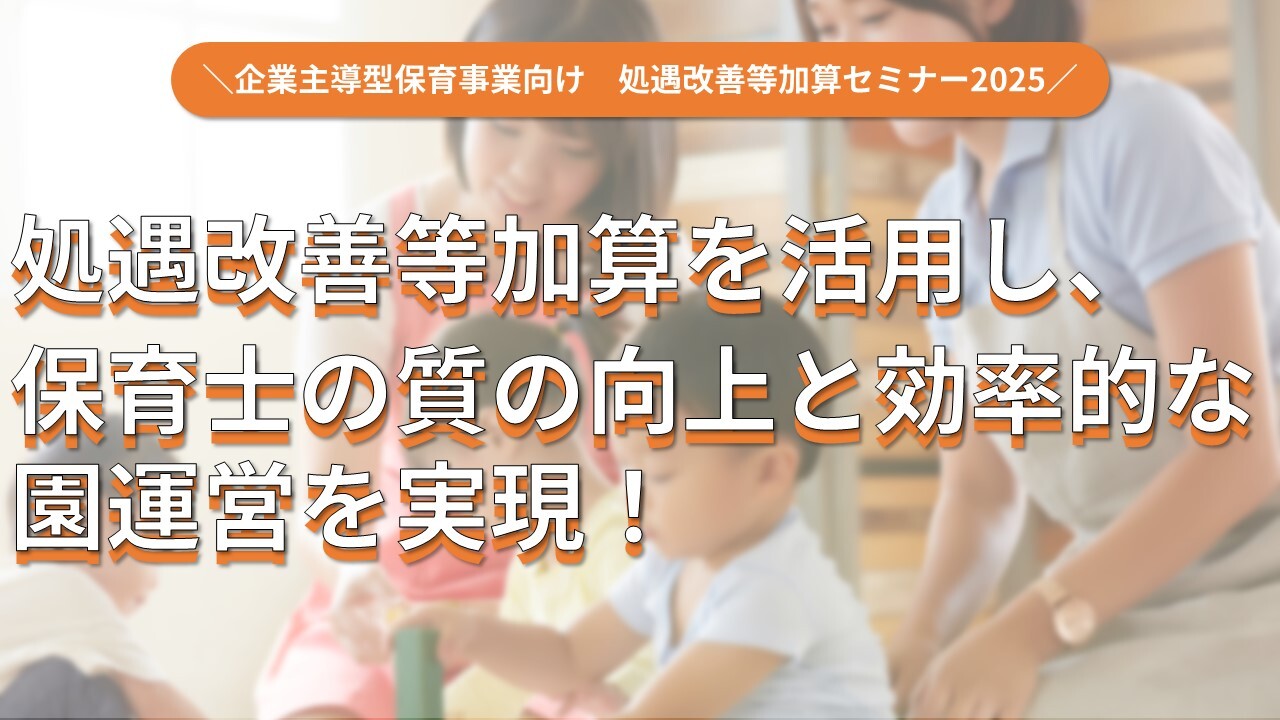
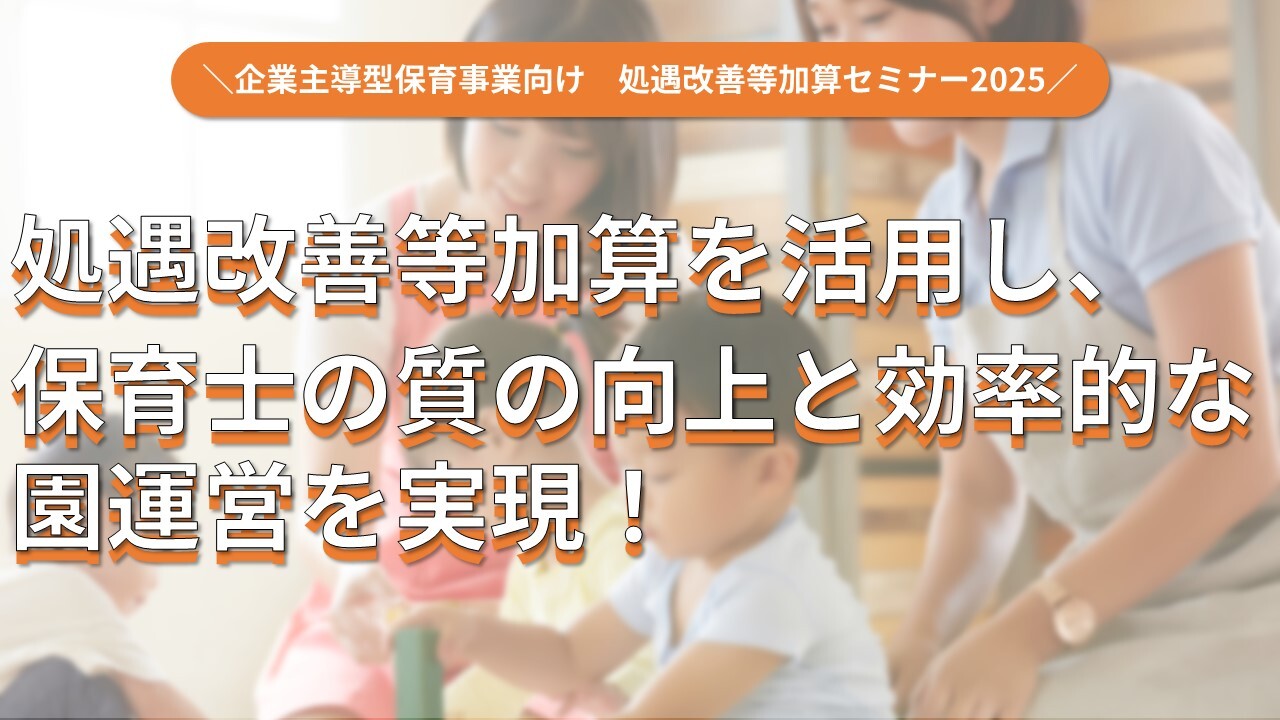
本日は企業主導型保育事業における処遇改善等加算の配分事例についてお伝えいたしました。様々な配分事例から園での効果的な配分方法を見つけていただけますと幸いです。
また、弊社では2025年9月に、企業主導型保育事業に特化した処遇改善等加算セミナーを開催いたします。
今回の内容に加えて、セミナーでしかお伝えできないより踏み込んだ実際の配分事例や、返還額なく、基準額以上の改善を行う秘訣などをお伝えさせていただきます。
本日のコラムを踏まえて、少しでもご関心のある方はぜひご参加いただけますと幸いです。