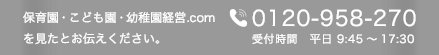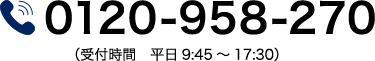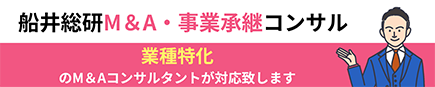【企業主導型保育事業向け】処遇改善等加算の返還を回避するために
いつも保育園経営.comのコラムをお読みいただきありがとうございます。
船井総合研究所 子育て支援部の小島です。
企業主導型保育事業を運営されている皆さまにとって、処遇改善等加算の運用は、毎年頭を悩ませるテーマではないでしょうか。年度完了報告での加算返還や過度な支払いが生じたという話をよく耳にするようになりました。また、専門的な労務監査や財務監査も年々厳しくなっており、適切な運用が強く求められています。
今回のコラムでは、こうした返還リスクを回避するための具体的なポイントを掘り下げていきます。処遇改善等加算を最大限に活用し、安定した園運営を実現するための一助となれば幸いです。
また、前回のコラムでは企業主導型保育事業のよくある処遇改善等加算の返還事例もお伝えしております。あわせてご確認ください。
企業主導型保育事業の処遇改善等加算を再確認
施設型給付や地域型給付の保育事業では処遇改善等加算が一本化されつつありますが、企業主導型保育事業では引き続き「処遇改善等加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」として継続されます。この制度のルールをきちんと理解することが、「まさかの返還」を回避し、加算を最大限に活用するための第一歩です。
まずは、それぞれの加算について確認すべきポイントを見ていきましょう。
処遇改善等加算Ⅰ
この加算は、保育士だけでなく、事務職員、調理員など、日常の保育業務に携わるすべての職員(非常勤職員含む)が対象です。役員は対象外ですが、法人役員を兼務する施設長で、給与規定に基づき給与が支払われ、実務を行っている場合は対象にできます。(使用人兼務役員)
賃金改善は、基本給、手当、賞与、一時金など幅広い給与項目で行うことができます。ただし、住宅手当や扶養手当のような生活補助的な手当、皆勤手当、早番手当のように勤務状況で変動する手当は対象外です。また、定期昇給分に充てることもできません。職員一人あたりの賃金改善額に明確な基準はありませんが、施設全体の賃金改善総額(法定福利費などの事業主負担額を含む)が、加算基準額以上である必要があります。
処遇改善等加算Ⅱ
この加算は、リーダー的役割を果たす中堅職員の専門性向上とキャリアアップを目的としています。主に「副主任保育士等」や「職務分野別リーダー等」が対象ですが、職務は問われないため、看護師や調理師なども含まれます。経験年数「概ね7年以上(副主任保育士等)」「概ね3年以上(職務分野別リーダー等)」はあくまで目安であり、柔軟な運用が可能です。
賃金改善は、基本給または毎月支払われる手当で行う必要があり、賞与や一時金での支給は認められません。
また、研修修了要件が段階的に必須化されています。
・副主任保育士等:令和7年度(2025年度)は「専門分野別研修」と「マネジメント研修」のうち3つ以上の研修分野の修了が必須です。
・職務分野別リーダー等:令和6年度(2024年度)から「専門分野別研修」のうち1つ以上の研修分野の修了が必須です。
この加算を取得するには、副主任保育士等と職務分野別リーダー等の両方に賃金改善を行う必要があります。
処遇改善等加算Ⅲ
この加算は、職員の賃金の継続的な引き上げ(ベースアップ)を目的とし、運営費から給与が支給されるすべての職員が対象です。ただし、処遇改善等加算Ⅰとは異なり、法人役員を兼務する施設長は対象外です。
賃金改善の合計額の2/3以上は、基本給または決まって毎月支払われる手当の引き上げによって行うことが求められます。
キャリアパス要件と給与規定の整備
処遇改善等加算を適切に運用するには、職員の職位や職務内容に応じた給与規定の明確化と、キャリアパス要件の遵守が重要です。新規申請時や処遇改善部分の変更時には給与規定の審査が必要となり、労働基準監督署への届出も確認されます。労働者が10人未満で届出義務がなくても、給与規定の作成と全職員への周知は必須です。
これらの点を踏まえ、計画的な運用と報告を行うことで、加算を最大限に活用し、安定した園運営を目指しましょう。
予期せぬ返還を回避!
企業主導型保育事業の処遇改善等加算は、職員の処遇改善に不可欠な助成金ですが、ルールを誤ると予期せぬ返還が生じる可能性があります。助成金を確実に受給し、安定した園運営を継続するために、以下の点に留意し、計画的に運用しましょう。
計画的な賃金改善と柔軟な配分
賃金改善総額が交付額を下回ると返還が生じます。法定福利費等の事業主負担増加額は賃金改善額に含めることができます。
加算Ⅰ:基本給・手当・賞与・一時金での改善が可能です。ただし、生活補助的手当や変動手当、定期昇給は対象外です。
加算Ⅱ:賃金改善は基本給または毎月支払われる手当で行う必要があります。ボーナス・一時金としての支給は認められません。
加算Ⅲ:賃金改善額全体の2/3以上を基本給または毎月支払われる手当の引き上げで実施する必要があります。
職員への適切な配分と育成
加算Ⅰ:全職員が対象です。役員も条件によっては対象となるため、しっかり確認しましょう。
加算Ⅱ:副主任保育士等と職務分野別リーダー等の両方への賃金改善が必須です。保育士以外に調理師、事務職員も対象となるため注意が必要です。経験年数はあくまで目安であり、柔軟な配分が可能ですが、研修要件が段階的に必須化しています。
正確な実績報告と監査対策
年度終了後の「処遇改善等加算実績報告」は申請が義務付けられています。要件不備が見つかった場合、支給された助成金の返還が必要です。また、年度報告・完了報告・実績報告は分割できず、一括での提出が必要です。
賃金台帳や給与規定等の証拠書類は5年間保管が義務付けられていますので、しっかり管理しておきましょう。監査で不適切な運用が判明すると返還や助成決定取り消しにつながります。専門的労務監査では職員への周知状況なども確認されます。
まとめ
企業主導型保育事業を運営する皆様にとって、処遇改善等加算は不可欠なものです。しかし、運用を誤ると助成金の返還リスクが生じます。確実に受給するためには、最新の要綱の確認、給与規定の策定、全職員への周知などが必須です。
賃金改善総額が交付額を下回ると返還となるため、法定福利費の増額分も含めて計画的な運用を心がけましょう。また、正確な実績報告と5年間の証拠書類保管も返還を避ける上で重要です。
このコラムが、皆様の園における処遇改善等加算の適切な運用の一助となれば幸いです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
・時流・業界動向
・処遇改善等加算
・収支改善
・企業主導型保育事業
・セミナー・研究会のご案内
企業主導型保育事業向け 処遇改善等加算セミナー2025
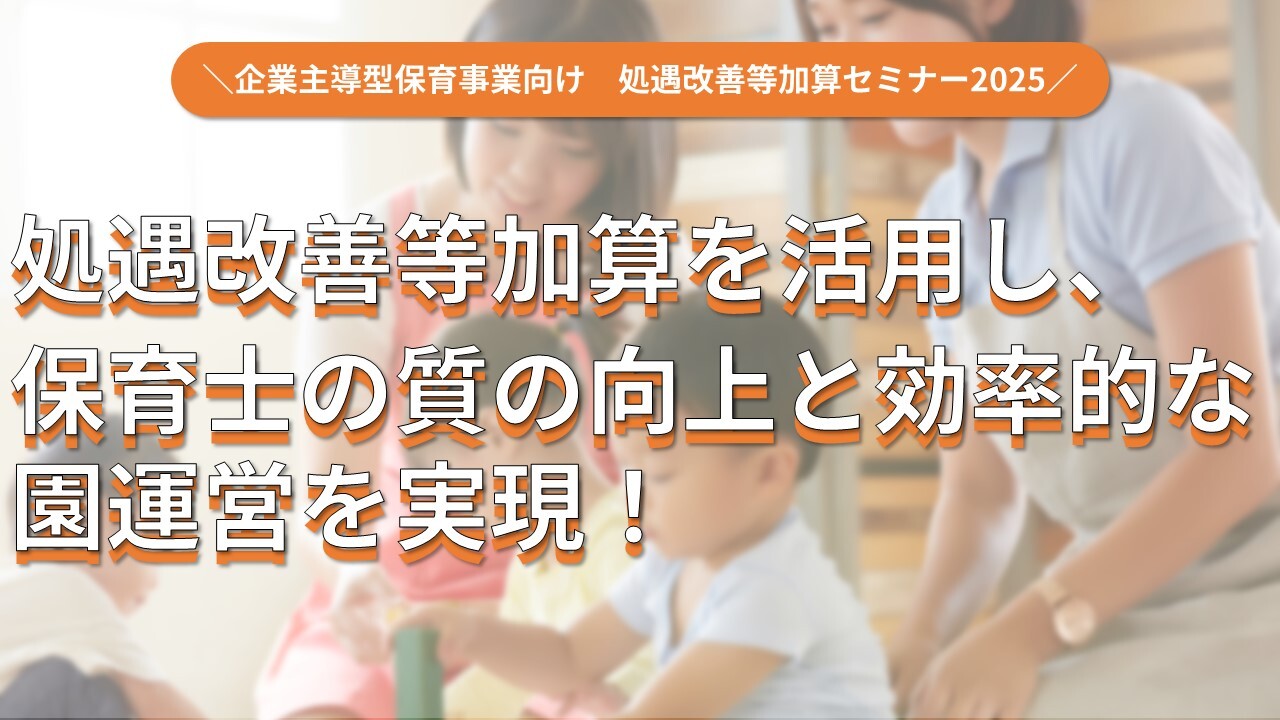
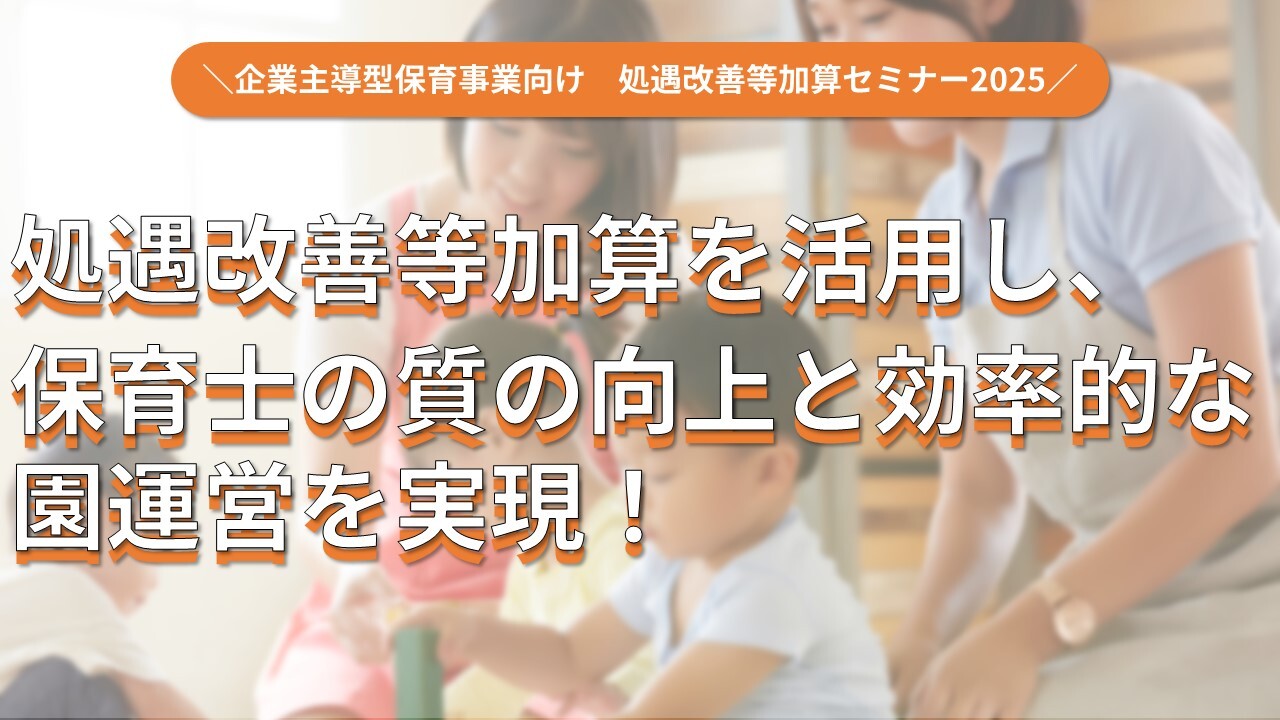
本日は企業主導型保育事業における処遇改善等加算の返還を回避するためのポイントについてお伝えいたしました。
現在、処遇改善等加算を取得されている方も、これから取得予定の方も改めて最新の制度を学び、園での効果的な活用をいただけますと幸いです。
また、弊社では2025年9月に、企業主導型保育事業に特化した処遇改善等加算セミナーを開催いたします。
今回の内容に加えて、セミナーでしかお伝えできないより踏み込んだ実際の配分事例や、返還額なく、基準額以上の改善を行う秘訣などをお伝えさせていただきます。
本日のコラムを踏まえて、少しでもご関心のある方はぜひご参加いただけますと幸いです。