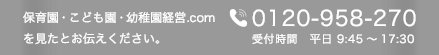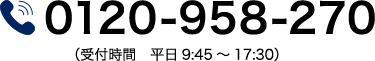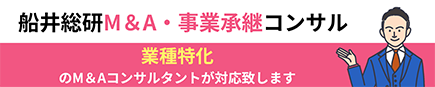「ここに通わせたい!」を引き出す園見学・説明会戦略
- テーマ:
- 園児募集
本コラムをお読みいただきありがとうございます。船井総合研究所の子育て支援部の張です。
暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしですか?
暑い夏を過ぎると徐々に来年に向けての園児募集活動を行う園も多いのではないでしょうか?
今回は園児募集においても、オフラインの施策として特に大事になってくる園見学・園説明会について考えていければと思います。
保護者の心をつかむ園見学・説明会の重要性
少子化が進む現代において、保護者に「ここに通わせたい!」と感じてもらうためには、単に施設を見せるだけでなく、保護者の心に響く体験を提供することが不可欠です。
園見学や説明会は、園の魅力を直接伝え、保護者の不安を解消し、入園希望を最大化するための極めて重要な機会です。
しかし、多くの園で、保護者が「わからない」と感じる点が多々存在し、その機会を十分に活かしきれていないケースが見受けられます。
集客・告知:保護者を引き寄せる効果的な情報発信
園見学・説明会の成功は、まず適切な集客・告知から始まります。オンライン施策(Instagram、公式LINE、Googleビジネスプロフィール、SNS広告、HPなど)とオフライン施策(チラシ、ポスティング、子育て支援イベント、園見学など)を組み合わせ、園の魅力を最大限に訴求することが重要です。
特にオフライン施策は、SNSを見て入園を決める人は少ない一方で、一度の来園で入園を決める保護者も一定数いるなど即効性があり、保護者の雰囲気を感じ取れるという園側のメリット、そして実際の雰囲気や保育者と交流できるという保護者側のメリットがあります。
しかし、残念ながら「やりがちNG事例」として、HPに案内がない、またはわかりにくい、自分が対象者なのか・どんなことを知れるのか情報を出していない、問い合わせが電話のみで園長など一部の人しか対応できない、といった点が挙げられます。これらの状況は、保護者の「そもそも見学させてもらえるのか不明」「問い合わせが電話しかない」「担当者がいないと受付ができない」といった不安を増大させます。
これに対し、「好事例」としては、まず対象者やターゲットを明確にすることが肝心です。
例えば、来年度の入園を検討中の保護者向けなのか、特定年齢の子ども向けなのか、などを明示します。次に、園内の雰囲気を写真で魅力的に見せることも非常に重要です。保護者として園選びで重視することの一つが園の雰囲気であり、視覚情報は非常に有効です。さらに、日時、時間、内容を可能な限り詳細に記載し、保護者が疑問なく参加できるよう配慮しましょう。
園の強みをわかりやすく簡潔に伝えることも忘れてはなりません。申込誘導のQRコードをわかりやすく配置し、HPやSNSへのリンクを掲載してスムーズな誘導を心がけることが、集客数を最大化する鍵となります。
参加者管理:保護者の不安を払拭するきめ細やかな対応
集客した保護者がスムーズに参加できるよう、参加者管理は極めて重要です。ここでは、保護者が感じる「申し込めたのかよくわからない」「何を準備していけば良いかわからない」「子どもを連れて行って良いのかわからない」といった不安を解消することが求められます。また、園側では、情報共有ができていないといった問題も起こりがちです。
「好事例」として、まず申込時には、見学の詳細を再度記載し、氏名等の基本情報に加え、連絡先を確実に取得することが挙げられます。さらに、子どもの年齢や入園希望年月を確認し、可能であれば比較検討中の他園名を聞くことで、保護者のニーズをより深く理解する手助けになります。また、自動返信で申込受付完了メールを設定することで、保護者は申込が受理されたことをすぐに確認でき、安心感が得られます。
加えて、見学日の3日前にはリマインドメールを送り、当日終了後には御礼・事後誘導メールを送ることで、きめ細やかなサポート体制を築くことができます。公式LINEを活用すれば、これらの情報管理やメール送付を簡単に行うことが可能です。
当日運営:園の魅力を最大限に伝える体験の提供
園見学・説明会の当日は、保護者が園の雰囲気を肌で感じ、保育者と交流できる貴重な機会です。しかし、「どこから園に入って良いかわからない」「挨拶がない・ウェルカム感がない」「情報が多すぎる・少なすぎる/時間が長すぎる・短すぎる」といった「やりがちNG事例」は、保護者の期待を裏切る結果となりかねません。
「好事例」としては、まず園前に園への入り方と歓迎を伝える立て看板を立てるなど、明確な誘導とウェルカム感を演出することが重要です。そして、職員全員に見学者が来ることを共有し、園全体で受け入れを行う意識を持つことで、保護者に温かい印象を与えられます。
当日のスケジュールを明確に提示することも必要です。例えば、土曜日の10:00から11:00の枠を設定し、冒頭挨拶と園の説明(25分)、園内見学(15分)、質疑応答(10分)、アンケート回答と個別質疑応答(10分)といった具体的な時間配分を示すことで、保護者は安心して参加できます。担当職員は園長だけでなく、複数の保育者で対応することで、保護者は「どんな人が日々保育してくれるのか」という疑問を解消し、保育者との交流を深めることができます。説明会資料、持ち帰り用パンフレット、感想アンケートなどの準備物も用意できますとより良いでしょう。
事後フォロー:入園への道を繋ぐ継続的なコミュニケーション
園見学・説明会は、当日で終わりではありません。保護者との継続的な接点を持つことで、入園への誘導数を最大化できます。
「やりがちNG事例」として、持ち帰り資料がない、参加後の連絡がない、入園に向けて何から始めればよいかわからない、園と気軽に接点を持つ場がない、SNSやブログの案内がない、といった点が挙げられます。これでは、せっかく芽生えた「ここに通わせたい!」という気持ちが薄れてしまいます。
「好事例」では、まず説明会資料や感想アンケートをしっかりと用意し、持ち帰ってもらうことで、見学後の振り返りを促します。そして、連絡先を取得し、定期的にアプローチをかけることが非常に重要です。具体的には、見学の当日~翌日には参加の御礼を伝え、1か月以内には次のイベント告知を行い、保育所申込期間には募集の告知を行うなど、時期に応じた情報提供を行います。
また、日頃からSNSなどで園の日常を継続的に発信し、保護者が気軽に園と接点を持てる場を提供することも大切です。ここでも、公式LINEの活用は、保護者への情報管理や送付を簡単にする強力なツールとなります。
園見学・説明会を単なるイベントではなく、「ここに通わせたい!」という強い入園意欲を生み出すためのプロセス全体として捉えていただきたいです。集客・告知から参加者管理、当日運営、そして事後フォローに至るまで、一貫した仕組み作りを行うことが、入園誘導数を最大化する鍵となります。
保護者の「わからない」を解消し、園の魅力を余すことなく伝え、信頼関係を築くことで、貴園の価値を最大限に高めることができるでしょう。本コラムが、貴園の園見学・説明会を見直し、より多くの保護者に選ばれる園となるための一助となれば幸いです。