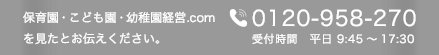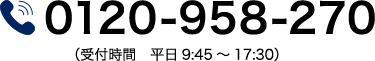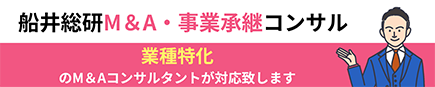いつもお読みいただきありがとうございます。
船井総研の永田屋でございます。
全国でいよいよ保育事業の公募が本格的に動き出す時期となりました。すでに選定に向けて準備を進めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、令和6年度の公募に顕著に見られる3つの傾向についてお伝えします。これらの傾向を理解することが、公募選定を有利に進めるための鍵となりますので、ぜひ最後までお読みいただき、今後の公募準備にお役立てください。
多様化する公募
今年度も公募が最も活発になる時期ですが、近年、公募の多様化が顕著になっています。数年前、待機児童が多かった頃は新設案件が大半を占めていました。しかし、現在は公立施設の民営化、医療的ケア児対応型、児童発達支援との併設型、講師連携型などの多様な類型が見られます。
この背景には、行政の意向として「保育の量から質への転換」があると考えられます。単に受け皿を増やすだけでなく、これまで手が届かなかったサービスや、地域のきめ細やかなニーズに応えたいという狙いがあるのです。そのため、行政の意図や狙いをしっかりと掴んだ上での公募対策が、これまで以上に重要になります。
「ピンポイント化」する公募
上記の多様化にも関連しますが、特定の類型に特化した公募や、新設であっても「〇〇駅から1km圏内」といった局所的な需要に対応する案件が多くなっています。
これは、全体として待機児童が解消されつつある中で、残りわずかな「足りないエリア」をピンポイントで埋めていきたいという行政の狙いがあるためです。また、資材高騰により施設整備に潤沢な予算が組めない中で、無駄なく効率的に整備を進めたいという意図も背景にあります。「そこを解消すれば整備は終了」という、最後の勝負となるエリアも出てきていると言えるでしょう。
「内向き化」する公募
待機児童解消に伴う施設整備のタイミングで、全国展開する事業者が外部から地元に進出してきた自治体も多くあります。地域にはないノウハウを持つ外部事業者に好印象を持つ自治体が多い一方で、地元事業者からの反発が根強いエリアがあるのも事実です。
こうした地元の声を踏まえ、その後の公募では「市内事業者のみ」といった条件を設けるなど、縛りをかける公募も散見されるようになりました。エリア外での選定を狙う場合は、チャンスが減少していることも加味し、早期からの接点づくりや調整がこれまで以上に求められます。
自治体の「こども計画」チェックの上早めの公募準備を
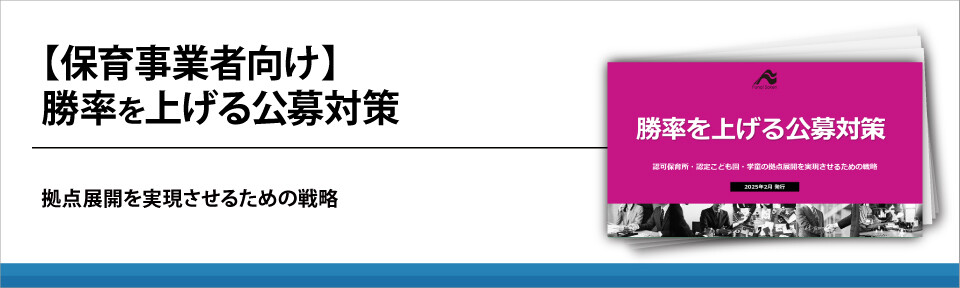
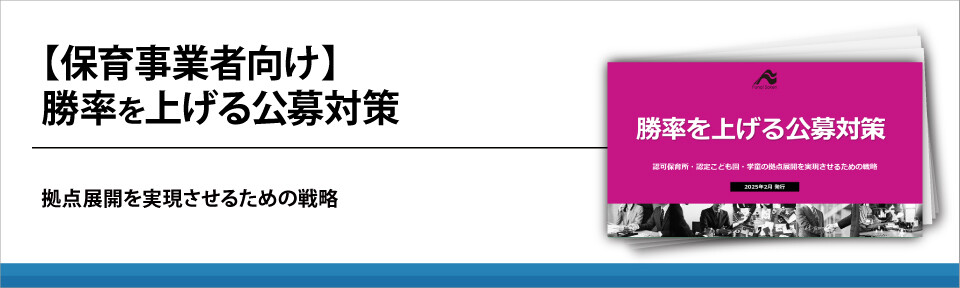
今年度の傾向として、上記3つのポイントを挙げましたが、当然ながら各自治体によって状況は異なります。
今年度より、新たに各自治体の「こども計画」が進行中です。この計画には、今後の施策の方向性や保育確保量の見込みが盛り込まれており、今後の行政の動きを把握する上で非常に有効な情報源となります。
実際に、この計画に基づき、各自治体がこの夏から具体的な動きを見せています。今後、公募の選定を狙っていきたい事業者の皆様は、ぜひお早めに各自治体の「こども計画」をご確認ください。
公募選定に向けた具体的なノウハウを無料のコンテンツとしてまとめました。ご興味のある方は、ぜひ以下のリンクよりダウンロードしてご活用ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。