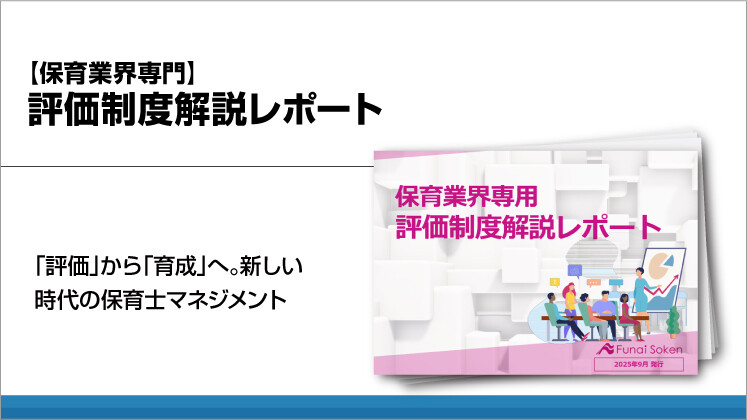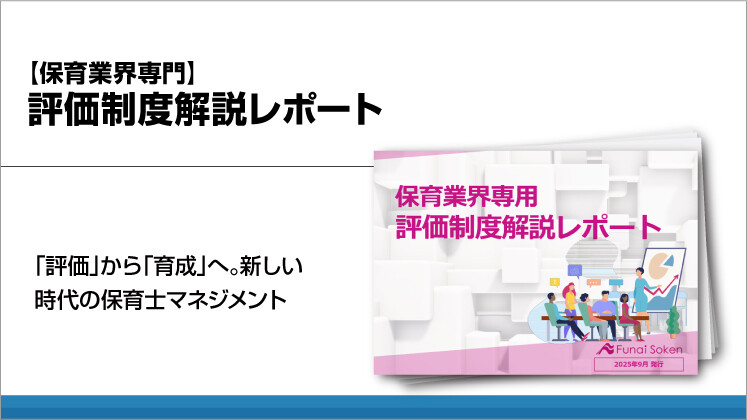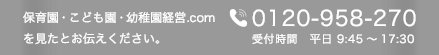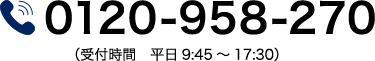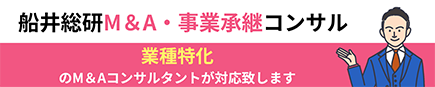いつも弊社の保育園・こども園経営.comのコラムをお読みいただきありがとうございます。
船井総合研究所の吉田健人(よしだけんと)です。
本日は、来年度以降の職員定着・育成につながる評価制度についてお伝えします。
令和7年度から処遇改善等加算が一本化され、区分①の要件としてキャリアパス要件が明確化され、また継続的な見える化施策の一つであるモデル給与の公開義務化等ともあわせて、
明確なキャリアパスの構築・評価賃金制度の運用がより重要になってきます。
そこで、今回のコラムでは、キャリアパス構築を行い、職員の育成を自動化することができる「評価制度」の構築についてお伝えします。
評価制度を形だけ運用する・単なる給与決定ツールとして使用するのではなく、育成の仕組み化の観点も取り入れて構築することで、法人の「求める人材像」と職員の「成長ステップ」が明確になり、
職員の努力の方向性を一致させることができます。
「評価」ではなく「育成」がセンターピンとなる理由
従来の評価制度の多くは、給与や賞与を決めるため、査定としての要素に重点が置かれていました。しかし、職員の過去にフォーカスする制度では、将来的な成長につなげることが難しくなってしまいます。
保育業界の制度の流れを踏まえたこれからの時代に求められるのは、「Plan(計画)→ Do(実行)→ Action(改善)」という成長サイクルを回すための制度です。
評価を「目的」ではなく、職員の成長を促すための「手段」として活用することで、職員の育成を自動化していくことが、今回提唱する評価制度構築の目的となります。
法人と職員の努力の方向性を一致させる、具体的なスキルマップの作り方
育成にも活用できる評価制度を作ろうと思っても、「もっと成長してほしい」という抽象的な期待だけでは、職員は何をどう頑張ればよいか分かりません。
まずは法人の中での理想の職員増を可視化し、求めるスキルを要件化した「スキルマップ」を作成する必要があります。
「スキルマップ」とは、法人が大切にする項目(例:法人理解、専門技術、保護者対応など)ごとに、「どのような行動ができるか」をレベル別に言語化(見える化)したものです。
(例:保護者対応)
Lv.1: 笑顔で明るく元気に送迎対応ができる。
Lv.3: 送迎時に子どもの状態確認の会話ができる。
Lv.5: 他職員の対応フォローや、個別面談が必要な支援ができる。
このように、「できる/できない」の二択ではなく、具体的な行動レベルで基準を明示することで、それが法人と職員の間の「共通言語」となり、目指すべき姿が明確になります。
管理者の負担を激減させる、集計方法について
スキルマップをもとにした評価制度運用で最も大変なのは、集計と分析の作業です。
ただ〇×をつける評価ではなく、基準を明確にした行動レベルで回答いただくため、
自己評価で1~5段階、上長評価でも同様に5段階評価と、結果が多岐にわたり、紙ベースでの集計では多大な工数がかかってしまいます。
今回お勧めする評価制度では、アンケートフォームを用いた集計の自動化を推奨しております。
これにより、例えば「自己評価と上長評価のギャップ」などがグラフで瞬時に「見える化」されます。
園長先生等の管理者は自動化で生み出された時間を、「職員との対話(フィードバック)」に使うことができるようになり、職員が次の評価までに日々の仕事の中でどこを、どのように頑張ればよいかが明確になります。
いかがでしたでしょうか?
上記のように、職員の給与を決める・職員を管理するために制度を使うのではなく、
明確な成長ステップ(スキルマップ)を示して人件費を投資として考えることで、
職員が自律的に育ち、それが法人・園の保育の質向上に直結するという考え方が、今回の評価制度のポイントです。
より詳細な作成方法を知りたい方は、無料でダウンロードできる小冊子にて評価制度構築のステップや分析方法、フィードバックについてまでを解説しておりますので、ぜひダウンロードいただけますと幸いです。
保育業界に特化した評価制度構築方法を解説!