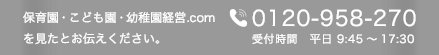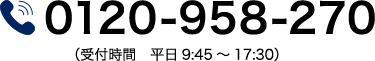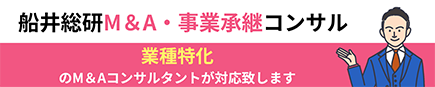皆様
いつも保育園経営.com のコラムをご愛読いただきましてありがとうございます。
船井総合研究所 子育て支援部の菅野 瑛大(かんの あきひろ)です。
今回は、「新入保育士の即組織人化」というテーマで、これからの保育園経営において非常に重要な考え方についてお伝えしたいと思います。
「保育士」である前に「組織人」であるという意識
新年度を迎え、新たな仲間を迎え入れた保育園も多いのではないでしょうか。 新しい職員がスムーズに園に馴染み、その力を最大限に発揮するためには、保育の専門性だけでなく、「組織の一員である」という意識を早期に醸成することが不可欠です。
これまでもコラムの中で何度かお伝えしましたが、職員の皆様に
「あなたのご職業は何ですか?」と質問してみてください。
多くの場合は、「保育士です」「幼稚園教諭です」といった職種名が返ってくるでしょう。 しかし、ここで重要なのは、保育士等の資格は「職種」であり、その前に「会社員(株式会社系)、団体・法人職員(社福・学法等)、公務員(公立園)」といった「職業」に所属しているという認識を持つことです。
このマインドセットがなければ、「一人の保育士として」という意識が先行し、「組織人である」という意識が見えづらくなってしまいます。 自らが所属する組織があるからこそ、自身の資格を活かすことができ、様々なことに低リスクで挑戦できる環境があるということを、新入職員にしっかりと伝える必要があるでしょう。
組織の一員としての自覚を促すための3つの質問
全職員の意識を上げるための3つの質問を改めてお伝えします。
新入職員に対して改めてこれらの質問を投げかけ、組織の一員としての意識を高めるきっかけとしましょう。
1.あなたの職業は何ですか?
冒頭にお伝えした通り、資格を活用した専門職は資格名=職業となってしまいがちです。
まずは組織を構成する一員であることを認知・理解してもらいます。
2.あなたの勤める園はどの制度のもとに運営されていますか?
認可保育所、地域型保育事業、幼稚園、認定こども園など、運営の根拠となる制度を少なくとも知っていただく、可能であれば自分の属している施設が規定されている制度については概要を理解してもらいます。
これを知らないということは、自分が提供しているサービスが何かがわからずに行っているに近い状況です。
「選ばれる園づくり」が保育業界でビッグキーワードになっている今、提供者が自分のサービスを知らないということは、致命的になっていくでしょう。
現場職員には少し遠い話のように感じられてしまうかもしれませんが、この意識づけが早いか遅いかで、今後の園“経営”が大きく変わってきます。
3.保育士(または幼稚園教諭等)は何のプロですか?
養成校などで資格獲得に向けて学んだ知識だけでなく、「勤めている法人・園の方針に即したものになっているか」という視点で、自身の専門性を説明できるように促します。
理論から実践に移行する際に「感覚」で理解をしていく部分もありますが、最初の段階で言語化して共通認識を持つことで「保育観の違い」といった負のマジックワードの出現を可能な限り抑えられるでしょう。
これらの質問を通じて、新入職員は「自分は組織の一員として、定められた制度の中で、法人の方針に基づいた専門性を持つプロフェッショナルである」という意識を育むことができます。
法人・園の「あり方」と「やり方」を明確に伝える
新入職員が組織の一員としてスムーズに業務に取り組むためには、法人や園の理念、保育方針、日々の業務の進め方(あり方・やり方)を明確に伝えることが重要です。
年度当初は、先輩職員から新入職員へ、様々な指導や教育が行われると思いますが、
「A先生とB先生から言われることが違う」といった声が出始めることがあります。
これは、「法人理念・教育保育理念→目標・方針→各種計画→左記を達成するための細かいやり方」といった考え方とその実現方法が、しっかりと伝わっていないことが原因です。
抽象度の高い理念を伝えるためには、具体化させてイメージできるように「言語化」することがポイントです。 経営者である皆様、法人として紡いできた想いや考えを、新入職員に対して、時流に合わせた言葉や考え方を基に、「日々の仕事に落とし込んで」説明することが重要です。
計画的なOJTとOff-JTによる組織人としての成長
新入職員を組織の一員として育成するためには、計画的なOJT(On-the-Job Training)とOff-JT(Off-the-Job Training)を組み合わせることが効果的です。
1.OJT①:認知
日々の仕事や業務を通して、どのような仕事があるかを認識する機会を提供します。
2.Off-JT:あり方の理解
その仕事がどういうものか、なぜそれを行うのか、法人・園としてどうあってほしいかを説明し、頭で理解する機会を設けます。
3.OJT②:やり方の理解
具体的にどのように対応するかを先輩職員が見本を見せたり、一緒に実践したりすることで、身体で理解する機会を作ります。
4.OJT③:行動
理解した仕事や業務を実際に新入職員が実行する機会を与え、先輩職員がフォローします。
このようなステップを踏むことで、新入職員は「認知→あり方の理解→やり方の理解→行動」という流れで、組織の一員として必要な知識・スキル・意識を段階的に習得していくことができます。
ポイントは「まずはやって見せる×意図まで丁寧に説明する」を徹底することにあります。
最重要点は「先輩方が理解する」ことである
新入保育士を早期に組織人として育成することは、保育の質の向上、職員の定着、そして選ばれる法人づくりに繋がる重要な取り組みです。
改めて整理すると、
・「保育士」である前に「組織人」であるという意識を浸透させる。
・3つの質問を活用し、組織の一員としての自覚を促す。
・法人・園の「あり方」と「やり方」を具体的に言語化して伝える。
・計画的なOJTとOff-JTを通じて、組織人としての成長を支援する。
これらの取り組みを通じて、新入職員が組織の一員として自信を持ち、主体的に業務に取り組めるよう、経営者・管理者はしっかりとサポートしていきましょう。
そして何よりも「先輩職員」が全員上記の内容を理解することが重要です。
特に、<「保育士」である前に「組織人」>という内容は、ベテランになるほど実は忘れがちな(ないしは、知る機会がなかった)ことが多いでしょう。
改めてマインドセットすることが、好循環を生むポイントなります。