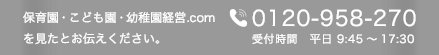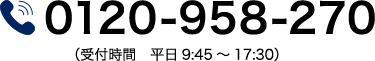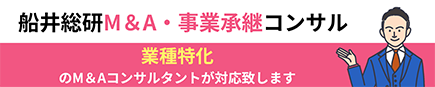皆様、いつもありがとうございます。
船井総合研究所の島崎です。
船井総合研究所では、毎年8月に研究会全国大会経営戦略セミナーを開催しております。
先週、多くの経営者の皆様にご参加いただき、無事に終了しましたが、
そこで得た学びをもとに一部をシェアさせていただきます。
なお、本日のメルマガでは、人口減少が進む現代において、
特に幼保業界が持続的に成長していくために不可欠な経営戦略と視点について、ご紹介いたします。
※少し、理論的になります・・・ご了承ください。
幼保業界が直面する課題と成長への道筋
「消滅可能性自治体*1」が全国1,729市町村の約43%にあたる744市町村に上り、
2020年から2050年にかけて若年女性人口が半減すると推計されるなど、
少子化は日本社会全体の喫緊の課題です。
*1:人口戦略会議「令和6年・地方自治体「持続可能性」分析レポート-新たな地域別将来推計人口から分かる自治体の実情と課題-」令和6年4月24日
このような状況下で、幼保業界もまた、
事業の存続と成長をいかに実現するかが重要な経営課題となっています。
しかし、成熟業界であってもイノベーションは可能です。
重要なのは、固定観念を捨て、明確な差別化を図り、戦う領域をはっきりさせることです。
アンゾフの成長マトリクスから探る幼保経営の可能性
幼保業界での成長戦略を考える上で、「アンゾフの成長マトリクス」は非常に有効なフレームワークです。
• 「市場浸透戦略」: 既存のサービスで市場シェアの拡大や、顧客一人あたりの購入金額・購入頻度を向上させる戦略です。
【幼保経営での実施策】園児募集機能の強化、延長保育の利用促進などによる保育料アップが挙げられます。
• 「新市場開拓戦略」: 新たな顧客層の獲得や地理的な事業エリアの拡大を目指します。
【幼保経営での実施策】学童保育の展開(民設民営/公設民営問わず)、特別支援を必要とする子どものケア(福祉領域への進出)、別エリアへの拠点展開(公募またはM&A)などが考えられます.
• 「新製品開発戦略」: 既存顧客へのクロスセルやアップセル、顧客の新たなニーズへの対応、製品ラインナップの拡充によるブランド強化を図ります。
◦
【幼保経営での実施策】課外教室の付加、国際バカロレア(IB)などの特色ある教育・保育コンテンツの導入が該当します。
• 「多角化戦略」: まったく新たな事業領域への進出により、収益源を確保し、事業ポートフォリオのリスク分散を目指します。
【幼保経営での実施策】M&Aによる別事業の展開などが考えられます。
幼保経営を支える学校法人・幼稚園の「強み」
学校法人や幼稚園は、その事業を安定させ、成長させるための多くの「強み」を持っています。
• ヒト(人的リソース): 教職員、事務職員、理事会、経営陣に加え、保護者や地域の人々も重要な人的リソースです。
• モノ(物的リソース): 施設、設備、教材、教具、土地などが挙げられます。
• カネ(財務リソース): 自己資金、運営費補助金、寄付金などが安定した経営を支えます。
• 情報: 教育・保育内容、各種データ、外部ネットワーク、情報発信ツールが強みとなります。
• その他無形資産: ブランド・評判、歴史・伝統、組織文化・風土といった無形資産も、長期的な成長の基盤となります。
• 圧倒的な税制上の優遇措置: 法人税が原則非課税、固定資産税などが非課税、寄付が集めやすいといったメリットがあります。
• 安定した経営を支える公的補助: 経常費補助金や施設型給付費、施設・設備の補助などが経営の安定に寄与します。
• 高い公共性と社会的信用: 教育への専念、永続性と安定性が高く評価されます。
これらの強みを活かし、市場のニーズと自園並びに自法人の長所を明確にすることで、
他園との差別化を図ることが可能です。
少子化時代の経営モデル:「総合子ども・子育て支援拠点構想」
船井総合研究所では、少子化時代における経営モデルとして、
「地域に生まれる全ての子どもを支援する」という理念のもと、
「総合子ども・子育て支援拠点構想」を提唱しています。
これは、0歳から5歳以上の子どもたちに対し、教育、保育、福祉の領域を横断的に支援する包括的な構想です。
具体的には、親子教室、未就園児教室、幼稚園、認定こども園、認可保育所、小規模保育、企業主導型保育、
病児保育、児童発達支援、放課後等デイサービス、放課後児童健全育成事業、教育付き学童保育、
課外教室・スクール事業などを包含しています。
この構想を通じて、地域の子どもたち全体を支えることで、
持続的な成長を目指すことができるでしょう。
最後に、変化の激しい時代において、ぜひ経営者の皆様には、
「フレームワーク(固定観念)を外し」、
常に新しい知識を取り入れ、
それらを実践していく機会を作っていただきたいと考えています。
このメルマガが、貴園の持続的な成長戦略の一助となれば幸いです。